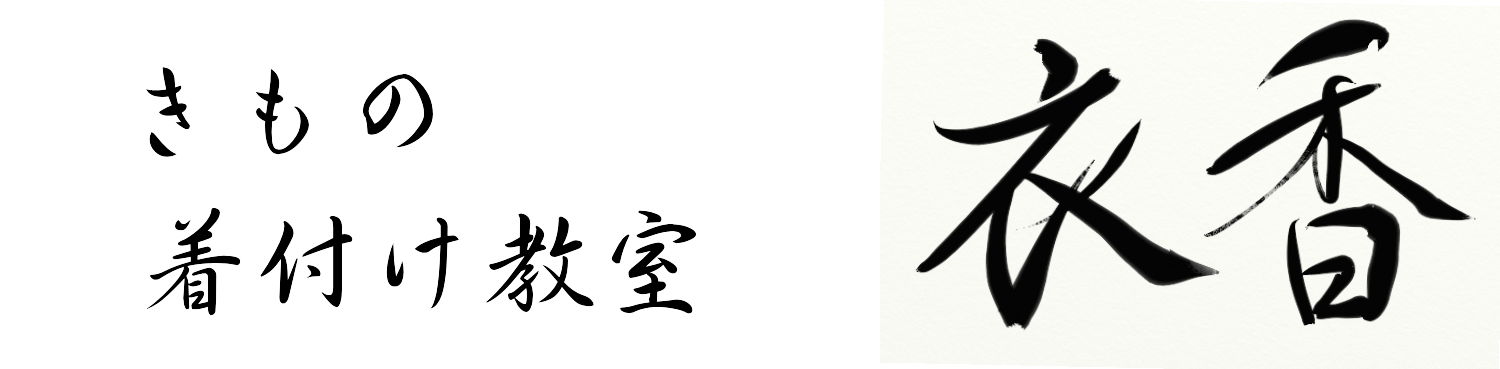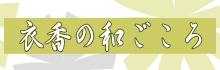未分類
明るく、気を抜かず、コツコツと!
2020年4月12日 未分類
今までに経験のない、春の一日をすごしております。 好きな帯結びに、半幅帯を使いお太鼓風に見せている「お福太鼓」があります。笹島寿美先生のご考案の結びで、腰を隠したい年代の方々に、人気が。。。 …
ポスティング ロード!
2020年4月11日 未分類
今朝の空には、縹色と白色が織りなす素敵な模様で出来ている。空の色や雲の大きさ・形・色などに、よくきものや帯の模様を想像して、遊ぶ! 人生の荷物は少なく軽くを、目指しているので、想像は色よい思いを与えてくれる優れもの。もし …
石鹸から思いを馳せる!
2020年4月6日 未分類
コロナ騒動で手洗いの回数が多くなりました。アルコールが手に入らないので、石鹸を使ってよく手を洗っています。ふと脳裏をかすめたのは、昔の石鹸はどんなものだったのかしら? 桃山時代に伝来して来たし …
きもの話
2020年4月4日 恋衣 (きもの&帯)未分類
冠婚葬祭などがないと会えない身内と、久々に懐かしい昔話に花咲かせた。 その人の鮮明な思い出は、八十三歳で暇乞いをした私の祖母の、背骨が真っ直ぐであったことでした! 祖母とは同居していたが、姿勢に関しては完全に失念していた …